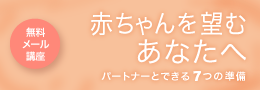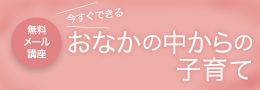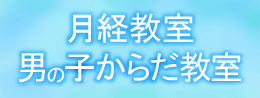2020年03月17日
■子宮のことを
細かく話していただいたので、
どんな造りになっているかは
わかったのではないかと思います。
性交渉や性病、または自分を守る術や
どんな人とだったら
性交渉をしていいのか?など
具体的な内容も聴きたかった。
2019年10月
■子宮のはなしを解りやすくご説明いただき、
娘も理解できたのではと思います。
2019年10月
■“命のリレー、命をつなぐ”といった視点が
とてもいいなと思いました。
2019年10月
■DVD“うまれるよ”をみて出産を思い出して
本当に出産できてよかったと思いました。
2019年10月
■うまく表現できなかったことを
“命のみち”“おそうじ”等
優しい言葉で伝えることを
学べてよかったです。
命はずっとつながっている
ということを解りやすく
教えて下さったこともよかったです。
2019年10月
■生理が始まることを“大人スイッチON”
という言い方がとてもいいなと思いました。
2019年10月
■出産前にお話を聴きたかったです!
おなかの中で赤ちゃんがいろんな準備を
していたことを初めて知って、
より赤ちゃんのすごさを感じました。
先生の話し方が素敵でスーッと
入ってきました。
2019年10月
2020年03月17日
■娘にどう話をしてよいかわからず、
でもそろそろ話をしないといけない!
というタイミングで話が聴けて
大変勉強になりました!
これから娘と
月経や性の話をするときの
参考になりました。
大人になっていく娘に同じ女性として
アドバイスしていけたらと思います。
(母:吉田まゆみ)2019年6月
■娘の月経のために
と思い参加しましたが、
お産を振り返る良い機会になりました。
帝王切開に少し
コンプレックスがありましたが
帝王切開をした病院の先生の言葉を
教えていただけて嬉しくなりました。
娘は大分前から、
やまがたてるえさんの
「13歳までに伝えたい女の子の心と体のこと」
を読んでいますが、
今日のお話や映像でより
具体的に学べてよかったと思います。
不登校中のため
学校で月経の授業を
受けないと思うので助かりました。
(母:KCO)2019年6月
■家庭ではなかなか
出産や生理について細かく
話をすることが出来ないので
(私自身がうまく説明できなさそうで‥)
今回とてもわかりやすく
丁寧に話をしてくださって
ありがたく思いました。
母・娘のディスかっションも
普段娘には話せないことも言う事ができ、
他のお母さんの話も聞けて、
娘には良い刺激に
なってくれたのではないかと
期待しています。
いつか来る日が、
慌てず心にいい余裕をもって
対応できることを祈りつつ、
何かあったらいつでも聞いていいんだよ
ということを実行してくれたらいいな
と思いました。
(母・S.Y)2019年6月
■私自身が母とあまり生理や
女性のからだについて話したことがなく、
相談しづらいなとずっと感じてきました。
娘とは気軽に話せて困ったときはすぐに
相談できる相手になりたいと思い
今回参加しました。
これをきっかけに、
月経教室でこんな話をしたね!とか、
月経や女性のからだ、性に関して
会話をしていきたいと思います。
(母・M.I)2019年6月
2020年03月11日
今年も3月11日がやってきた。
あれから満9年たったが対応策は進んでいるのだろうか?
もしもの時に一番に守るべき人たちは、未来をつくる子どもたちとおなかの赤ちゃん。胎児とママが一心同体であるだけでなく、小さな子どもとママも一緒でなければ子どもを守ったことにはならない。
………………

もし、災害が起こったら、一番に保護される必要のあるのは誰?
赤ちゃんや幼い子(と母)そして妊娠中の女性だと思う。乳飲み子を守るにはお母さんといっしょでないと無理だし、幼い子供も母といっしょにいてこそ安全、安心にすごせる。
そして何より妊娠中の人は最優先で大事にされる。
そんな先進例が、ここにある。それぞれの区や市で、これが当たり前になるように、できることを、それぞれの場所でやっていこう。
====================
災害時に妊産婦・乳児の命を守る施設
【文京区のプロジェクト~妊産婦・乳児救護所】
男女協働・子ども家庭支援センター課長
男女協働・子ども家庭支援センター課長 鈴木秀洋さん
2013年、文京区は地域防災計画に、「妊産婦」と「乳児」専用の救護所を盛り込みました。
災害時に職員及び助産師を派遣し、妊産婦・乳児の心身をケアする拠点とする取組みです。設置の経緯と、クリアしなくてはならなかった問題などについて、
設置の当時、文京区危機管理課長で、現在は、男女協働・子ども家庭支援センター課長の鈴木秀洋さんにお話しを伺いました。
東日本大震災の現場から得た教訓
「母子救護所」の必要性を感じられたのはなぜですか?
鈴木さん:2011年3月11日に東日本大震災が発生しました。
震災後、先遣隊(危機管理課長)として釜石に入り、避難所の様子を目の当たりにしました。
特に妊産婦さんや、乳児の安全安心が守られていないことに、ショックを受けました。
乳児の泣き声を気にしたり、妊婦さんが安心して出産することも難しいために、避難所を去っていく乳児の親や、妊産婦さんたち。
その後、避難所に入った職員の報告や東北3県の避難者受入れを通して、文京区の仕組みづくりに向き合いました。
最初はプロジェクトとして、構想を固められたそうですね。
鈴木さん:震災後の課題は山積みでした。
また首都直下型地震がいつ来るともわからない中、新しい予算取りのための資料作成や、審議会等の設置を行っている時間的・労力的余裕はありませんでした。
そこで、任意の(使命感ある地域の人達と)プロジェクトチームを立ち上げました。医師、助産師、看護師など、専門家をはじめ、子育て支援をしているNPOや、地域のパパ・ママにも集まってもらい、昼夜なく知見を集め、「妊産婦・乳児救護所」のプランを練っていきました。
災害弱者の中で、妊産婦と乳児をなぜ重視するのか
壁になったことはありますか?
鈴木さん:社会的弱者と言われる人々(障がい者、高齢者など)の中で「なぜ、妊産婦と乳児を優先するのか」というところでした。
もちろんそれぞれ優先しなくてはなりませんが、東日本大震災の教訓として、特に関心がもたれなかったのが、妊産婦と乳児だと強く感じていました。
そこで、妊産婦等への優先対策の必要性について、いくつもの文献を当たりました。また様々な災害・危機管理の講演会・シンポジウムにも出かけ、エビデンスを集めました。
その中で(当時)東京臨海病院院長山本保博先生からは国際基準では、災害弱者に、
「C(hildren)、W(omen)、A(ged people)、P(atients & poor people)、F(oreingn people)」を
位置付け、対象をとるべきとされていること、その中でもC及びWは妊産婦・乳児をさすと解釈すべきであり、最優先弱者として対策の優先順位を上げなければならない
(『東日本大震災を踏まえた予想される都市災害への医療対応策』と題する講演(2012年8月2日日本危機管理士機構第三講義)と教えられたことは、
その後の対策を進める上で非常に参考になりました
(そのほかにも、スフィア・スタンダードなどもひとつのエビデンス)。
そして、まずは、間違いなく
最優先課題である妊産婦・乳児に対する具体的制度設計を直ちに行おうと考えました
(当時必要性について記述はありましたが、詳細な具体的制度設計については示されたものはなく、
文京区の具体的制度設計はその後、東京都や国にも採り上げられ、全国から問い合わせがあり、
有する地域資源ごとに形を変えて全国に広まっていきました。このことは非常にうれしかったです。)。
国際基準は、災害弱者を以下のように定め、子供・妊産婦を明確に位置付けている。
Children
Women
Aged People
Patients
Poor People
Foreign People
東京臨海病院山本保博院長『東日本大震災を踏まえた予想される都市災害への医療対応策』より
「妊産婦・乳児救護所」の設置場所として、区内の大学と提携したというのも、珍しい取り組み方だと思います。
鈴木さん:避難所としては、小・中学校の体育館が主に指定されています。
ただ、命に関わり、特別な配慮が必要な人達への上乗せ対応として、区内の大学、特に女子大学に協力を仰ぎたいと考えました。
女子トイレの数が確保されているなどの利点がありますし、実習設備としてベッドや入浴施設を兼ね備えている大学や、福祉・介護系をもつ大学は、学生の協力という点でも理解を示してくれました。
もちろん最初から二つ返事というわけにはいかず、大学には何度も足を運び、調整し、協定を結びました。
「どの場所を指定できるのか?」、
「防災無線通信機や備蓄をどこに置いて管理を行うのか?」、
「そのサイクルは?」など、
災害という緊急時の、学業との優先関係や、事故の場合の責任負担など、法的関係を何度も詰めました。
考え方のベースは同じでも、大学ごとに議論すべきポイントは異なりました。
同じように、人の派遣を依頼した東京都助産師会館や東京都助産師会、順天堂大学病院等との間でも、単なる紳士・握手協定ではなく、具体的な課題をクリアしてから協定を結びました。
大学との避難訓練も実施
協定後は訓練などしているのですか?
鈴木さん:上位の地域防災計画や、男女平等条例に書き込み、法的位置付けを明確にし、具体策と連動させました。
災害時、誰がどこの避難所、母子救護所の担当になるのか、職員配置のリストも作成しています。
母子救護所は、その場所で安全に出産できることが必要ですから、担当職員は、妊産婦の理解等の研修を受けています。
出産をサポートする助産師さんにも、母子救護所に駆けつける担当表を求めています。
協定を結んだ4つの大学には、①粉ミルク、②アレルギー用粉ミルク、③紙オムツ、④お産セットなどの備蓄もしています。
備蓄のスペースは基本的に文京区が管理しており、
使用期限になったら入れ替えるなど、定期的に中身のチェックも行っています。
災害時の情報発信などはどのように行われますか?
鈴木さん:防災無線、衛星電話、安心・防災メール、ツイッター等のほか、
文京区では日常的な子育て情報を発信している「きずなメール」を利用して、災害時に有用な情報発信をする予定です。
※ きずなメールについての詳細は以下のとおり
http://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kosodate/kosodate/merumaga.html
鈴木さんは現在は、男女協働課長、子供・家庭支援センター課長という立場にいらっしゃいますが。
鈴木さん:いつ来るか分からない災害に備えるには、まさに日頃の制度設計、訓練、意識によります。
今後は、構築した制度をメンテナンスしつつ安定運用・バージョンアップしていくことが大切だと思っています。
私は、男女協働(ジェンダー・人権)セクションと、
子供・家庭支援センターセクションを指揮する責任者として、日々全力で、子供の命を守っております。
====================
2020年01月11日
2020年は自ら身体を運んで
出かけて行く年
2021年は迎える年
そんなふうに私自身の
2020年と2021年をとらえています。
早速ですが
今日11日から連休はさんで
スリランカに行ってきます。
臨床瞑想法の先生のグループに参加して
行くのですが
シギリヤロックの上での瞑想というのが含まれていた!
2017年に両膝の手術をして
今ではどこでも歩ける私ですが
山登りなんかしたことがない私の体力で、
階段とはいえ約200mの岩を登れるのか?
と急に気になり、
12月中旬から
「インターバル速歩」というのを始め
今のところ毎日続いています。
サッサカ歩きで3分間、
ゆっくり歩きで3分間、
また速足で3分間、と繰り返します。
最低でも30分(速歩合計15分)以上
週に4回以上、6ヶ月ほど続けると
基礎体力が上がるそうです。
はじめから30分歩こうとか
1時間歩こう、というのでなくて
とりあえず3分歩く。
スマホのタイマーを3分にセットして
速足3分、ゆっくり3分の繰り返しで
どんどん歩いてみました。
そうしたら不思議なことに
30分なんてあっという間、
1時間では物足りなく
1時間半になってしまうくらい
すいすい歩けるんです。
外は寒いですが、まず最初の速歩3分で、
身体が温かくなってきます。
ゆっくりの時には、あちこち
緩めるようにいろんな歩き方を試したり
木や花や鳥を眺めたり
飽きるということがありません。

この時期、東京の日の出は6時50分ごろ
夜明けはその30分くらい前なので
6時20分ごろから歩きだし
近くの水元公園まで行き
日の出を見るのを目標として
1時間をめどに帰ることにして続いています。
私は果たして
シギリアロックに登れるのか?
次には結果報告をいたしますね。
浅井あきよ・記