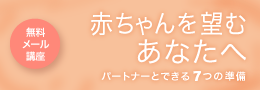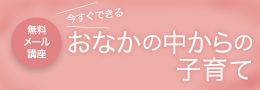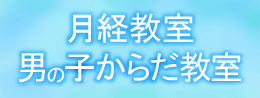ブログ
2019年03月18日
お花見のご案内です。
今日から春のお彼岸
21日は春分の日、彼岸のお中日です。
そのころには、桜の花もちらほら咲きはじめるのでしょう。
まだ、桜の木は静かです。
こぶしの白い花は今が満開。
白モクレンとも言いますが、
毎年この花が終わるころ桜が咲きます。
今日は「お花見」のおしらせです。
お彼岸も明けた3月26日(火)
午後2時から
★桜の開花の様子で日程追加しました
3月30日(土)
午後2時から
虹のへやから見えるお寺の本堂の中から、
欄干越しにお花見をしましょう。

桜を見上げるのでなくて
横から、または見おろすというお花見です。
私が抹茶とお菓子を用意てお待ちいたします。
(正式のお茶のお点前ではありません
気楽にどうぞ)

でもせっかく、本堂の中なので
お茶とお菓子とお話だけでなく、
本堂の中の大きなカネの音を聴いて
(このカネは吊鐘ではありません)
その余韻の響いている中(20秒ほど)
心静かにカネの響きを味わう、ということもしましょう。
詳細とお申込みはこちらから

(浅井あきよ・記)
2019年02月15日
2月12日 虹のへやで
やまがたてるえさんを囲んで
【女性のための保健室】を開きました。
以下やまがたさんのブログより引用
*********************************
大人の保健室〜女性のための保健室〜
2019年02月12日(火)
本日 開催させていただきました(^^)
開催して本当に本当に良かった!
心のぽかぽかする
安心安全な場になった
子どもの頃に
保健室があったように
大人になっても、保健室があっていい
お腹痛い…って
休むように
当たり前に休んでいいし
いっぱい手に持った荷物を
一旦置きに来るような
そういう
場所があっていい

参加する人達によって
毎回違う場になるこの企画も
これからも
定期的に開催していきます(^^)
本日ご参加いただきました皆様
本当にありがとうございます^_^
あきよ先生が
ぽかぽかの米ぬか温湿布を持ってきてくれたり
アロマを持ってきてくださって
優しい保健室になりました^_^
やまがたてるえ
***********************************
以上
また開催して欲しいという声もあがっています。
そのときには、あなたもどうぞ。
(浅井あきよ・記)
2019年02月08日
立春を過ぎてまもなく
おひな様を出しました。
毎年、レッスンルーム、玄関などに
この時期、おひな様を飾っています。
おひな祭りにちなんで
レッスンルーム虹のへやで
「大人のひな祭り」を
3月1日金曜日の夜7時から
開くことにしました。
お仕事かえりの方も参加できる時間です。
(子ども連れは参加できない時間でごめんなさい)
三砂ちづる著
「少女のための性の話」という本の中に
ひな祭りと「白酒」の話や
「菱餅」の意味が出てきます。
ちょっとドッキリのその話もご紹介
しますね。
あなたのおひな様は
今、どこで、どうしていますか?
3月1日の夜は
ひな祭りの前々日
おひな様に桃の花と菜の花をお供えして
お待ちします。
白酒と甘酒はよく間違えられるのですが
この日は
ほんものの白酒(アルコール度10%)
を用意します。
江戸時代から白酒をつくっているという
豊島屋さんの白酒です。
でも、お酒はちょっと、という方のために
糀から作った甘酒(もちろんノン・アルコール)
も揃えておきますよ。
その他おひな様に合いそうな
軽い食べものも用意しておきます。
大宴会ではなく
飲食付の「おはなし会」です。
おひな祭りは女性のお祭り
かつて少女だったもの同士で
集まりましょう。
(浅井あきよ・記)
(受付開始は、2月12日午後より
「へその緒の会」HPお知らせ欄に)
2019年02月01日
「胎教レッスン」の浅井あきよです。
先日、2人目を妊娠中に
私のレッスンに参加した方と
ばったり会いました。
いま幼児のお子さんは、
本当に素敵な輝くような子どもです。
冬なのでコートの下に隠れているとはいえ
ママは大きなおなかでした。
「(予定日は)いつですか?」
と聞くと
「来週木曜日に帝王切開なんです!」
とのこと。
子どもを迎えに
急いでいるところでしたので
ほんの一瞬でしたから
「じゃ元気で!」と言って別れました。
私のレッスンのことを
いろんな人に紹介してくれていたりしたので
このレッスンの価値は
認めてくれていると思うのです。
たぶん(私の想像なのですが)
帝王切開と決まっているから、、、というのが
3人目の時はレッスンに来なかった理由
なのではないかな?
と思いました。
以前にも、ほかのママに
「私、帝王切開って決まってますから。
(だから、いいです)」
と言われたことがありました。
帝王切開も立派なお産。
私、否定したりしてないよ。と
思っているのですが、、、、、。
「へその緒の会」の浅井あきよさんは
「自然派のお産のひとだから」って思われていて
帝王切開って決まっている人が
来にくいのかな?
ふと、そんなことを思いました。
帝王切開でも経腟出産でも
おなかの赤ちゃんは
おなかの中にいる9カ月間
日々いっしょに生活しているのだから
その時間が大事。
その中で、時には
おなかの赤ちゃんに集中する時間も
持てるといいね。
胎教レッスンって
赤ちゃんを大事にする時間であると同時に
ママ自身を大事にする時間
私はそんな風に思っています。
*「胎教レッスン」「おなかの中からの子育てレッスン」
ここでは同じ意味に使っています。
*写真は、
竹内正人著「ママのための帝王切開の本」
事前に知っておくと安心できる本です。

以前、娘のお産が帝王切開になると聞いて
相談に来た方におすすめしたところ
不安が解消したと言われました。
(浅井あきよ・記)
2019年01月26日
今日は「小学校に日時計を!」という話題です。
このタイトルは私が付けたものですが
もととなった文は
「和の舞」の千賀一生(ちが かずき)さんが
縄文暦に関して書いています。
以下のメルマガです。
なるべく、そのままご紹介しますね。
(スマホなどでも読みやすいように、
改行は私の方でさせていただきました)
以下 千賀一生さんからです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
みなさん、おはようございます。
年の初めの月ですので、
暦について、もう少しふれておきたいと思います。
私は田舎で育ったため、
幼少期は一日中畑で過ごすことがほとんどでした。
家族はおにぎりを作って畑に行くのですが、
食いしん坊の私は、
何度も家族に
おにぎりはいつ食べるのと
しつこく聞くために、
祖母は畑に着くと
私のためにまず日時計を作ってくれ、
棒の影がここに来たらおにぎり、
ここに来たら帰るよと教えてくれ、
土いじりをしながら
太陽が時計の幼少期を過ごしました。
人工物がない広々とした畑では、
基本的に存在するものは大地と太陽の二つです。
このなにもない中にいると、
広い空間の全体が刻々と変化し、
見渡す限りの空間の生きているような
変化を感じます。
大きな命の懐の中にいるような
感覚になります。
毎年それが繰り返されると、
この懐には
一年で大きな鼓動が生じているのが
わかります。
冬の太陽と
夏の太陽はまったく違うのです。
都会にいると、
時を数値でとらえがちですが、
このような中にいると、
時は、数値ではなく、
大自然の脈のように感じます。
私が生まれて初めて理解した時計は、
機械の時計ではなく、太陽の時計。
現代の子供たちは、
いきなり機械の時計の見方を教えられ、
数値で時を理解する育ち方をしますが、
私はこれをとても不自然に感じます。
縄文人が
冬至を最大の節目と認識していたことは
遺跡からわかりますが、
なぜ、冬至なのかが
私には経験的感覚でわかります。
これはまず、
計算しなくても誰の目にも
当たり前にわかるからなのです。
遮るもののない自然の中で生活していると、
自然界や太陽の運行をじかに見て
生活します。
当然、
冬至の節目はいやでもわかるのです。
太陽の昇る位置がずれてゆき、
折り返して逆行するポイントに
何かの意味を感じるのは自然の感覚です。
ましてや
その節目に人の生死が多く生じますから、
重要な日と認識されるのです。
さらに、もう一つの折り返しポイントと、
両者を結ぶ中間でも生死が集中しますから、
四つの節目は、
自然な流れで重要と認識されてきます。
(生死が集中するということは、
生きている人の中にも
小さな生死が生じているということです。
これが節目のリズムをもたらします)
ただ、縄文の大きな特徴は、
集落の全体が
この太陽の運行に合わせて作ってある点です。
たとえば
日の出の東の門の柱の影は、
冬至の日に集落中央に至り、
夏至に中央から最も離れます。
集落中央近くの柱の影は、
朝は集落の西に、
昼は北、
夕方は東に向かい、
日時計の役を果たします。
集落そのものが日時計であり、
カレンダーでもある仕組みです。
これは、
彼らが時というものを、
この上なく尊んでいたからです。
現代のカレンダーの節目は、
自然界の運行とは不一致です。
それは、
私たち人間のもつリズムとも
不一致ということです。
大陸由来の旧暦の暦も、
太陽の運行とは不一致です。
縄文暦は、
この私たちの原点のリズムを取り戻せたら
という思いで作成したものです。
私は、幼少期を思い出すと、
太陽の下に土まみれで過ごした日々が
本当に幸せであったと思います。
大地と太陽は、
私たちを無条件で幸せにしてくれます。
そして、
幸せにあるべき自然のリズムを
人間にもたらしてくれます。
都会にいると
この大地と太陽のリズムから
外れてしまいがちですが、
それを取り戻すことが大切であると思います。
ぜひ今年も縄文暦を
ご活用いただけたらと思います。
そして、
時には大地の上で土まみれの一日を!
[chiga-message:0133] 大地の暦 より
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以上、千賀一生さんのメルマガからでした。
縄文暦のおススメなのですが
私はこれを読んで
小学校に日時計を!
と強く思いました。
日常に日時計を置きたいと思っても
庭に日時計を置ける家がどれくらいあるでしょうか?
とても少ないと思います。
マンションのベランダでも
時間によっては
日が差さないということがあるでしょう。
そこへ行くと、小学校は
広い校庭を持っていることが多いので
その一角に日時計を置き
小学生に日時計の読み方を教えたらいいと思います。
できればその日時計は
わかりやすく
美しいものであってほしい。
子ども時代を思い出すときに
思い出されるようなものであってほしいと思います。
そしてそれを教える先生も
単なる理科の一教材ではなく
私たちが
地球の上に住む生物の一員であり
太陽の恵みを受けて生きていること
さらに、日本なら
地球の上の日本の緯度が
どんなに恵まれたものであるかなども
合わせて伝えてほしいと思うのです。
(浅井あきよ・記)
2019年01月25日
今年も1月23日に総会が
開かれました。
寒咲の水仙と蝋梅の香る、寒の半日。
へその緒の会の年度の切れ目は、
1月1日〜12月末日
という区切りです。
2年に一度、役員の改選があり
今年は理事に新しく
助産師の やまがたてるえさんが入りました。
高瀬江里子さんが退任し
(ほかの形で参画は続けますが)
新しい理事メンバーは
浅井あきよ(代表理事)
中澤さちこ(副代表理事)
山形照恵(理事)
となりました。
やまがたてるえさんのプロフィールはコチラ
へその緒の会を支える人たち
総会は
昨年度の報告
今年度の計画と
この理事の改選、と
型通りといえば型通りに
つつがなく進行しました。

で、それだけでは
せっかく一堂に集まる機会の少ない人も集まっているのだから、
ただ総会だけではつまらないでしょう?
そこで
毎年そのメンバーの一人が講師となり、何かしら
行っています。
私がイメージワークを行ない体験してもらった年もあります。
昨年は
なかざわさちこさんによる
『大人のための誕生学』でした。
今年は、やまがたてるえさんによる、
教育最前線の話。
2020年に教育指導要領が
大きく変わる事を知ってます?
というところから始まり
いま、そして2年後2020年。
6年後2025年、
さらに2045年、など
未来に、このような事が予想されている。
公開されている内閣府の資料を
スクリーンで見ながら、、、
このような学校以前の社会の変容のお話があったのちに、
いま、そして、2年後に起きる教育の変化の問題が、
たった1時間でよくこの密度という内容で語られました。
途中でクイズがあったり
参加型の楽しいレクチャーでした。
さらに、それだけでは、単なる知識で
右耳から左耳へと抜けてしまいそうなところを
教育要領の変化の目玉になっている
アクティブラーニングの一例として、
では、どうしたらいいか?
あなたの意見が反映されるとしたら、何をしますか?
という設定で、
二人組になって政策を出すというミニワークをしました。
この日は時間がなかったので
ここまでで終わりでしたが
これを付箋に書いて、出しあい、
全体でまとめることもできます、と。

一時間ピッタリお勉強をした後、
玄米粥を食べる会になりました。
七草粥の日からは離れましたが、
茹でた菜の花をのせたお粥に
様々なトッピング。
梅干し
しそゆかり
米ヌカベースのふりかけ
(白ゴマ、刻み海苔入り)
生わかめ
柚子の入った赤大根の漬物
削り節
ちりめんジャコも。
それぞれのお好みで
粗食ながら、色取り豊かな食事に。

40分でゆったりと食事をしたのち
手早く片付け午後1時にはお開きとなりました。
総会は参画会員と顧問会員だけですが
そのあとの会員の集いは
賛助会員も参加できるのです。
(浅井あきよ・記)
2019年01月22日
まずは、短歌を一つ紹介します。
“山梔子の朱実とらむと声あげて
指さすほどに 子は育ちたり”
これは、母 小山静代が詠んだ歌。
“子” は 3月に生まれて
抱っこされている 私です。
赤い実を「あっ、あっ」と言って指さしたそう。
特別にどうということのない短歌ですが、
これはあきよちゃんの事なのよ
と言われて育ったので
クチナシには、特別の思い入れがあります。

クチナシは初夏に香り高い白い花をつけますが、
秋〜冬、朱色の実をつけます。

たまたま、母は短歌を残しましたが、
短歌でなくても物語りのように
子どもに、
「あなたが赤ちゃんの時に」とか
「小さい時に、、、」と
まだ記憶にないころの
ほのぼのする小さなエピソードを
映像になるように繰り返し聞かせるのは、
子どもの根っこを育てることになると思います。
(浅井あきよ・記)
2019年01月21日
先日(1月19日夜)
「リーディング
~エドガー・ケイシーが遺した、人類の道筋~」
という映画を観てきました。
https://dev.plus-spiral.biz/hesonoo/wp-admin/post.php?post=3332&action=edit#
エドガーケイシー(1877~1945)は
催眠状態で病気の人から身体情報
(病気の原因など)とその対処方法を
知ることが出来た人。
エドガー自身は自ら語ったことを記憶しないので
必ず聞き取る役割の人がいました。
処方は、食べ物、からだの歪みの調整
たとえば仙骨が曲がっているのを直すなど
で、不治の病が劇的に治ったりしています。
現在膨大な記録が分析されて
その、基本4原則は
頭文字をとって【CARE】
と言われています。
C:Circulation(循環)
A:Assimilation(同化)食物を消化吸収する力
R:Relaxation/rest(休息)
E:Elimination(排泄)
ここでは言葉を紹介するにとどめますが
たいへん納得のいくもの。
病気と食事の関係や
病気と背骨の歪みの調整(整体)は
別々の治療方法として受け取られることも多いのですが
ケイシーの処方では、一人の病気を治すために
食物も背骨の歪みもの矯正も
総合的に扱われています。
ケイシー自身は治療行為はせず
潜在意識で
読み取り、伝える役割に徹した人です。
【がん】については
血液の劣化ががんを引き起こす
と言っています。
血液の劣化には4つの特色があって
1、血液中の酸とアルカリのバランス(酸性に傾く)
2、酸素供給能力が落ちる
3、老廃物の除去能力がなくなって老廃物が増えること
4、凝固能力の劣化
(凝固する力が落ちることで、免疫細胞が働きづらくなる)
以上はがんとの関係ですが
今、認知症の改善にもケイシー療法の
効果が出ているということです。
知りたいですね。
私はエドガーケイシーという人がいたことは
30年くらい前から知っていましたが
ケイシーの研究財団が今もアメリカにあり
さらに日本にもセンターができて活動しているということは
今回この映画を観て始めて知りました。
映画に登場する
光田 秀(日本エドガーケイシーセンター会長)氏が
とても穏やかな笑みをたたえた表情の人なのが
印象的でした。
(参考になる本)
【すべてはここに始まりここに帰る
エドガーケイシーの超リーディング】
白鳥哲(映画・リーディング監督)
+光田秀(上述)の対談

エドガーケイシーは1945年に亡くなっています。
その後の世界は
もっと、農薬はじめ
汚染がもっとひどくなっているわけで
排泄の大事さなどは
一層、意味を持っているのでは?
と思います。
(浅井あきよ・記)
2019年01月10日
【おとなの保健室】について
子どもの頃、
あなたにとって保健室はどんな場所でしたか?
学校という場の中にありながら、教室とは違う場所でしたね。
体温計などあるけど、病院やお医者さんとも違う。
困ったとき、何か助けてもらえる場所、ではありませんでした?
タイトルに【おとなの保健室】
と書きましたが、
実際は、
【にんぷさんの保健室】と
【女性のための保健室】という2つの会のことです。
今回、2月12日(火)に、初めて開きます。
担当は
助産師のやまがたてるえ さん。
やまがたてるえ さんは、
助産師で
「ぽかぽか子宮のつくり方」など
5冊もの本の著者であり
現役2児の母でもあります。
やまがたてるえ さんについてはこちら
【にんぷさんの保健室】は
その名の通り、
妊娠中方を対象としています。
多くの妊婦さんは、
病院で妊婦健診をして、
病院でご出産を迎えます。
病院ではなかなか聞けない、
日常の悩みや、
家族・パートナーシップのことなども共有しながら、
日々の生活の過ごし方などで
改善できるマイナートラブルなどを、
具体的に考えていく時間になります。
たとえば、
妊娠中にこんなことをしていいの?
産後はどうすごしたらいいの?
出産の不安がなかなか取れずに不安の日々…
本当に産後に準備しなくてはいけないものってなに?などなど
安心安全な気持ちで、いっしょに語り合いながら過ごす、
保健室のような相談会です。
【女性のための保健室】では
いろいろな年齢、立場の女性が参加できます。
女性特有のお悩みだけではなく、
変化するライフサイクルの中で、
心と体のアンバランスを感じて、
でも病院に行くほどでもないけれど…と
思っている女性はたくさんいるのではないでしょうか?
保健室のように、
気楽に集って安心した気持ちで、
病院などでは聞きづらいお話を、
笑って楽しく温かな気持ちで語らう相談会です。
妊娠を希望される方も、子育て中の方も、専門職の方も、
どんな方でも気楽に集える会です。
どちらも、お申込みは下記よりお願いします。
【にんぷさんの保健室】
【女性のための保健室】
(浅井あきよ・記)
2018年12月21日
もうすぐ、クリスマス。
町には、電飾があちこちに輝いていますね。
ところであなたがこどもの頃、
サンタさんは来ましたか?
私は、両親ともに仏教徒でしたが
サンタさんだけは来ました。
12月25日の朝、
枕もとに、
包みを見つけたときの嬉しさは
はっきり覚えています。
小学校2年生くらいまでは
本気で信じていましたし、
これは親が、と気がついてからも
4才年下の妹のためにそっと黙っていました。
クリスマスの前に、
22日は冬至ですね。
「冬至に柚子湯」の習慣は、すばらしいと思います。
冬至じゃなくても柚子湯に入りたいと
私は思うのですが、結局
冬至の日だけになります。
柑橘の香りは、気分を爽やかにしてくれますね。
蜜柑を食べる時、私たちは意識していませんが、
皮を剥くときの香りも
味わっているのですね。
年末年始、
車で遠出をする機会には
ぜひ、車に蜜柑を積んでお出かけ下さい。
というのは、
車で渋滞に巻き込まれたり
そうでなくても、長いこと車に乗っていると
子どもなんかとくに機嫌が悪くなったり
ぐずったり
大人でも
イライラすることがありますが
そんな時、
蜜柑の香りと
甘さを含んだ酸味が、気持ちもカラダも
リフレッシュさせてくれます。
ひんやり冷たいと、なおいいですね。
柑橘の香りの効果は、
アロマセラピーなどでも証明されていますが、
アロマオイルでなくても
蜜柑の皮を剥くだけで
食べるだけでいいので
こちらが、簡単。
蜜柑の香りでリフレッシュ
ちょっと、思い出してくださいね。
(浅井あきよ・記)